三陸海岸大津波(吉村昭)
こんにちは、たけうちです。
昨年5月のあるネット記事で、吉村昭の「三陸海岸大津波」という本の存在を知り、手に取りました。本の帯には「吉村記録文学の傑作」と書かれています。記録というと客観的、文学というと主観的なイメージがして、やや相反するような感じもしましたが、読んでみると、そこは十二分に納得できました。
吉村昭は三陸沿岸を旅する中で耳にした津波の体験談をきっかけとして、三陸地方の津波を調べようと思ったらしく、それが「三陸海岸大津波」となって昭和45年に発刊されました。
三陸では明治以降の近代だけでも大きく3度、明治29年・昭和8年・昭和35年に津波に襲われています。それぞれ、「明治三陸地震」「昭和三陸地震」「チリ地震」などで検索をすると、当時の壊滅的な惨状を写す写真がたくさん見つかります。明治から100年以上が過ぎた平成にあっても、”津波後”の街の姿はなんと酷似していることか。
そして吉村もこの3つの大津波を素材としましたが、「三陸海岸大津波」はネット上で見つかるそれら当時の写真を超えて、よりなまなましく、よりリアルに津波被害を描写していて、文字の力を見せつけられました。現実を写す写真よりも、さらにリアルに迫ってくる文字表現。
文章のほとんどは、被災者のインタビューや当時の記録文書、子どもたちの作文で構成されていて、極めて客観性が強いにも関わらず、吉村の大津波に対する恐れや、また津波災害を乗り越えようとする力強い住民たちへの畏敬が、ぐんぐん伝わってきます。
この「吉村記録文学の傑作」は、本棚の一番目に止まるところに置いておくことにします。

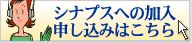





こんにちは。
「三陸海岸大津波」ですかぁ~。
よく「歴史は繰り返される」と言われますが、やはり昔の人の語り継ぎは、ただの「物語」ではなく「体験」から生まれた事なのかもしれませんね?
今回の東北大震災の映像は、私が考えた想像をはるかに超える大災害の映像でした。
でも、
>文章のほとんどは、被災者のインタビューや当時の記録文書、子どもたちの作文で構成されていて、極めて客観性が強いにも関わらず、吉村の大津波に対する恐れや、また津波災害を乗り越えようとする力強い住民たちへの畏敬が、ぐんぐん伝わってきます。
のように体験した人達の話を聞くとさらに恐怖心の感情も伝わってきます。
これからは、先人の「語り継ぎ」をただの「昔話」で終わらさず、「教訓」として活かした街づくりをしないといけないのかもしれませんね。
http://www.youtube.com/watch?v=sN1IfSpiasY
コメント by 9時から男 2012年3月14日 9:00 PM
9時から男さん、おはようございます。
そうですね。被災地から遠い鹿児島にいると、実生活ではなかなか災害の実感がわきづらいですが、常に関心を持って見聞きし、話していかないとな…と思いました。
コメント by たけうち 2012年3月20日 10:03 AM